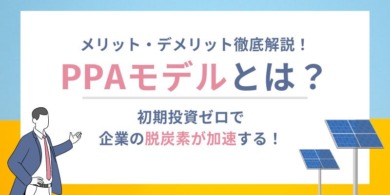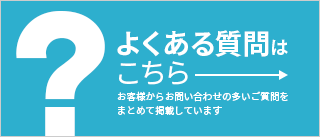産業用太陽光発電システムの導入件数が増加しており、多くの法人が自家消費による電気代削減やCO2排出量削減に取り組んでいます。
一方、産業用太陽光発電システムの設置は大規模な設備投資になるため、費用面が気になる方も多いのではないでしょうか。そこで今回の記事では、
- 設置費用がどれくらいか分からない
- 維持費にどれくらいかかるか分からない
- 費用を抑えて導入する方法を知りたい
という課題をお持ちの法人に向けて、産業用太陽光発電システムの設置費用について解説します。
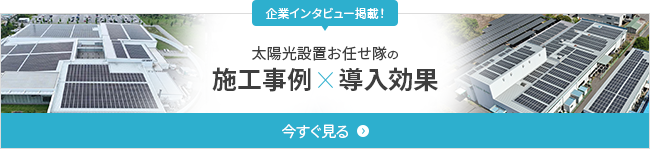
目次
産業用太陽光発電の設置費用
地上に設置する場合の相場
経済産業省の公開資料によると、地上に産業用太陽光発電システムを設置する場合の相場は以下のとおりです。
| 太陽光パネル | 9.9万円 / kW |
|---|---|
| パワーコンディショナ | 2.9万円 / kW |
| 架台 | 3.9万円 / kW |
| その他の機器 | 1.6万円 / kW |
| 工事費 | 7.8万円 / kW |
| 設計費 | 0.3万円 / kW |
| 接続費 | 1.8万円 / kW |
| 土地造成費 | 1.5万円 / kW |
(2023年度の実績値)
容量ごとの設置費用の目安
上記価格を参考にした場合、地上設置型太陽光発電システムの容量ごとの設置費用の目安は以下のとおりです。
| 設置容量 | 地上設置の費用 |
|---|---|
| 30kW | 891万円 |
| 50kW | 1,485万円 |
| 100kW | 2,970万円 |
屋根に設置する場合の相場価格
屋根に産業用太陽光発電システムを設置する場合の相場価格は以下のとおりです。
| 太陽光パネル | 8.4万円 / kW |
|---|---|
| パワーコンディショナ | 3.2万円 / kW |
| 架台 | 2.3万円 / kW |
| その他の機器 | 1.7万円 / kW |
| 工事費 | 6.9万円 / kW |
| 設計費 | 0.1万円 / kW |
| 接続費 | 0.4万円 / kW |
(2022年度の実績値)
容量ごとの設置費用の目安
上記価格を参考した場合、屋根設置型太陽光発電システムの容量ごとの設置費用の目安は以下のとおりです。
| 設置容量 | 屋根設置 |
|---|---|
| 30kW | 690万円 |
| 50kW | 1,150万円 |
| 100kW | 2,300万円 |
(参照元:令和6年度以降の調達価格等に関する意見|調達価格等算定委員会)
工事費用が増加するケース
設置条件によって、追加費用が発生するケースを紹介します。
ケース1.キュービクルの設置・改造工事
キュービクルとは、発電所から送られてくる高圧電力を、施設で安全に使用できる電圧に変換する機器です。
高圧以上の電気を扱う施設で太陽光発電の自家消費を行う場合、キュービクルを接続する工事が必要になります。キュービクルの容量が不足している場合、新しいキュービクルの設置または既存キュービクルの改造工事が必要になります。
キュービクルを新たに設置する場合と、改造工事をする場合の費用は以下のとおりです。
| 新しくキュービクルを増設 | 150万円〜200万円 |
|---|---|
| 既存のキュービクルを改造工事 | 50万円〜100万円 |
キュービクルは改造工事で対応した方が費用が安くなります。
設置費用を抑えるため、キュービクルの容量が不足する可能性を考慮して改造工事に対応できる業者に依頼するほうがよいでしょう。
ケース2.屋根の補強工事
屋根に設置する場合、屋根の状態に応じて補強工事が必要になることがあります。費用は、屋根材や工事の内容によって異なります。
| 葺き替え工事 | 4万円~6万円 /㎡ |
|---|---|
| 塗装工事 | 2千円~4千円 /㎡ |
設置費用を抑えるために、経年劣化や耐久性に不安のある屋根に太陽光発電を設置する場合は、建築に精通した業者や修繕工事も同時に対応できる業者に依頼するのがよいでしょう。
産業用太陽光発電の維持費
太陽光発電システムは、点検・メンテナンス・修理・保険料などランニングコストが発生します。
それぞれの維持費の内訳と相場を紹介します。メンテナンス費用
容量ごとに想定される年間のメンテナンス費は、以下のとおりです。
| 30kW | 15万円 /年 |
|---|---|
| 50kW | 25万円 /年 |
| 100kW | 50万円 /年 |
メンテナンスは、「50kW未満でFITを利用しない発電システム以外」は法定点検が義務化されています。
しかし、義務化の有無に関わらず性能を維持するために、メンテナンス費用を計算しておきましょう。
太陽光パネルの清掃費用
産業太陽光発電のパネルは野外に設置され、砂埃や鳥のフンにより発電効率が低下する可能性があるため、定期的な洗浄清掃が必要です。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 基本料金 | 1万円 |
| パネル1枚あたり | 500円~1,000円 |
システム交換費用
太陽光パネルやパワーコンディショナなどの設備故障時に必要なシステム交換費用について説明します。
| 部品 | 寿命 | 交換費用目安 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 太陽光パネル | 20~30年 | – | – |
| パワーコンディショナ | 10~15年 | 30~40万円/台 | メーカー保証期間内であれば無償交換可 |
保険料
産業用太陽光発電は、動産総合保険、施設所有者賠償責任保険、休業損害保険への加入が推奨されます。
各保険料の目安は以下の通りです。
| 保険種類 | 年間保険料目安 |
|---|---|
| 動産総合保険 | 初期費用の2.5%~3.5% |
| 施設所有者賠償責任保険 | 初期費用の0.3%~3% |
| 休業損害保険 |
産業用太陽光発電にかかる税金
法人が太陽光発電システムを導入した場合、以下のような税金の支払いが発生します。
| 償却資産税 | 税額は・取得価格・発電出力・設置場所・耐用年数などによって決定される評価額によって変動するため、詳しくはお問い合わせください。 |
|---|
設置費用を抑える方法
方法1.海外メーカー製のソーラーパネルを使用する
以前は海外製品に耐久性や発電効率の不安がありましたが、技術向上により、安価で高品質なソーラーパネルが手に入るようになりました。
産業用は数百枚設置することが多いため、ソーラーパネルの単価を抑えることで、総額を大きく抑えることができます。
方法2.補助金を利用する
補助金を利用することで、初期投資を大幅に抑えることができます。2024年度に公募される補助金は、たとえば以下のようなものがあります。
| 補助金名 | ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業(環境省) |
|---|---|
| 対象設備 |
|
| 補助率・上限額 |
|
| 補助金名 | 需要家主導太陽光発電導入促進事業(経済産業省) | |
|---|---|---|
| 対象設備 |
|
|
| 補助率・上限額 |
|
|
その他にも、さまざまな補助金制度が設けられています。 採択されれば、投資回収期間を大幅に早められるため、自身が利用可能な補助金は導入前にチェックしておきましょう。
産業用太陽光発電の最新の補助金情報は、こちらの記事で紹介しています。
方法3.複数業者の見積もりを比較
平均設置費用はあくまで目安であり、実際の費用は業者によって大きく異なります。
そのため、複数業者から見積もりを取り、比較してから依頼する業者を選ぶことがおすすめです。
見積もりの比較ポイント
見積もりを比較する際、安さだけで決めるのは避けましょう。質の悪い機材が使われていたり、アフターサービスが疎かである危険があるためです。
具体的には以下の点をチェックしましょう。
| 設備の種類と品質 | 発電量・耐久性・メンテナンスのしやすさなどを確認。電気代削減効果やランニングコストに影響します。 |
|---|---|
| 工事内容と工期 | 工事内容や工事期間を確認。施設の営業停止期間などに影響する場合があります。 |
| 保証内容 | 万が一の故障や不具合の際に、どの程度保証されるかを確認。保証期間も確認しましょう。 |
| アフターサポート | メンテナンスや保守などのサービス内容を把握しておきましょう。 |
発電効率や耐久性の高い製品は費用がかかりますが、長期的には費用対効果が高くなる可能性があります。
業者がどのような基準で、どのような機材を使用しているかしっかり確認しましょう。
太陽光発電業者の選び方は下記の記事をぜひ参考にしてください。
方法4.税制優遇を利用する
太陽光発電の導入には、下記のような優遇措置が設けられています。
| 中小企業経営強化税制 | 即時償却または設備取得価格の最大10%を税額控除 |
|---|---|
| 中小企業投資促進税制 | 設備取得価格の最大30%の特別償却または最大7%の税額控除 |
| 固定資産税の軽減措置 | 対象設備の固定資産税が2分の1に減免(最大3年間) |
| カーボンニュートラルに向けた投資促進税制 | 対象設備の設備取得価格の5%〜10%の税額控除または50%の特別償却(最大3年間) |
産業用太陽光発電の節税に関する詳しい解説はこちらの記事で紹介しています。
方法5.PPAモデルを利用する
PPA(Power Purchase Agreement)とは、電力販売契約の略で、PPA事業者に無料で太陽光発電システムを設置してもらう代わりに、発電された電気は購入するというモデルです。
簡単に説明すると、以下のようになります
設置費用が0円
電力購入契約をもとに、PPA事業者がすべての設置費用を負担するので、0円で太陽光発電システムを自社に導入できます。メンテナンス費・管理も不要
PPA事業者が設置した太陽光発電システムは、PPA事業者が所有権を持つので、管理業務やメンテナンスもPPA事業者がおこないます。発電された電気は購入する
発電された電気は、PPA事業者から購入することになります。
PPAの詳しい解説はこちらの記事で紹介しています。
設置費用を抑えた実例
当社の実例を紹介します。
実例1|補助金の活用
設置費用の約30%を削減

| 法人名 | 株式会社 瀬戸水産 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県 |
| 補助金による補助率 | 設置費用の約30%を補助 |
| その他 |
|
神奈川県で水産加工工場を運営する「株式会社瀬戸水産」様は、神奈川県の補助金「かながわスマートエネルギー計画」を活用し、設置費用の約30%を削減して導入しました。
実例2|税制優遇の活用
2つの税制優遇を利用して、わずか2年で投資回収

| 法人名 | 株式会社 ナカヱ |
|---|---|
| 所在地 | 和歌山県 |
| 利用した税制優遇 |
|
運輸・倉庫業を運営する「株式会社ナカヱ」様は、太陽光発電システムを新設倉庫に導入しました。
2つの税制優遇を利用し、太陽光発電の設置費用を約2年で回収することに成功しました。
実例3|PPAモデルの活用
0円で太陽光発電を導入

| 法人名 | R.R.Conys株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 宮崎県 |
| 設置費用 | 0円(PPAモデル) |
| その他 |
|
「R.R.Conys株式会社」様が運営するカフェ店舗は、PPAモデルを利用し、太陽光発電システムを0円で導入しました。
まとめ
1.産業用太陽光発電システムの平均設置費用
| 地上設置型 | 29.7万円/kW |
|---|---|
| 屋根設置型 | 23万円/kW |
2.設置費用を抑える方法
- 海外メーカー製のソーラーパネルを使用する
- 補助金を利用する
- 複数業者の見積もりを比較
- 税制優遇を利用する
- PPAモデルを利用する
業者によって製品や工事費用が異なるため、複数業者の見積もりを比較してから依頼先を決めましょう。
太陽光発電導入なら当社にお任せください!
- 豊富な施工実績
- 当社は、創業29年・太陽光発電施工において累計6,500件以上の豊富な実績がございます。長年にわたり培ったノウハウを活かして太陽光発電発電システムの導入を徹底サポートいたします。
- 屋根の高度計算や修繕も対応可能
- 当社は、創業時からリフォーム事業も営んでおります。屋根上への太陽光発電システム導入では、必要に応じて高度計算や修繕工事などの対応も可能です。
- 補助金申請サポート
- お客様が利用可能な制度の調査から書類制作、申請業務まで徹底サポートいたします。
まずは無料シミュレーション
まずは無料で、概算費用・導入効果をシミュレーションいたします。
お客様にとって導入メリットが少ないと判断した場合も、事実に基づいた情報を提供し、無理な営業は行いません。ぜひお気軽にお問い合わせください。