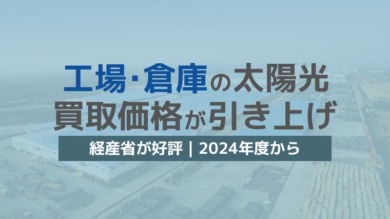再生可能エネルギーの1つである太陽光発電は、発電した電気の使い道で3つに分類可能です。
そしてここ数年は、家庭・企業ともに発電した電気を売る「売電型」から、発電した電気を自ら消費する「自家消費型」への移行が進んでいます。
この記事では、企業・法人向けに太陽光発電の3つの分類をご紹介し、さらに自家消費型太陽光発電のメリットや、注目される理由を解説します。
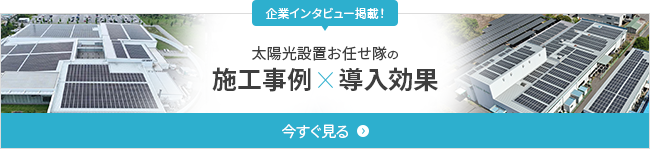
目次
太陽光発電の種類は発電した電気の使い道で3つに分類可能
全量売電型
全量売電型は、太陽光パネルで発電した電気をすべて売る方法です。
産業用太陽光発電の場合、固定価格買取制度(FIT)の認定を取得すれば、20年間は固定価格で電力会社に売電できます。
2019年度までは10kW以上の設備において全量売電が可能でしたが、2020年度以降は制度の改訂により、全量売電ができる発電所は以下のように変更されています。
- 設置容量50kW以上
- ソーラーシェアリングのみ10kW以上
2023年度に固定価格買取制度に認定された場合の、全量売電型の単価は以下のとおりです。
| 設置容量 | 売電単価 | 売電期間 |
|---|---|---|
| 10kW以上50kW未満(ソーラーシェアリングのみ) | 10円 | 20年間 |
| 50kW以上250kW未満 | 9.5円 | |
| 250kW以上 | 入札により決定 |
余剰売電型
余剰売電型は、発電した電気を自ら消費しつつ、余った分は電力会社に売る方法です。
設置容量が50kW未満の場合に適用されます。
2023年度に固定価格買取制度に認定された場合の、余剰売電型の単価は以下のとおりです。
| 設置容量 | 売電単価 | 売電期間 |
|---|---|---|
| 10kW未満 | 16円 | 10年間 |
| 10kW以上50kW未満 | 10円 | 20年間 |
また注意点として、2020年度以降は余剰売電型に以下2つの条件が追加されました。
- 発電した電気の30%以上は自ら消費すること
- 自立運転が可能なこと(災害などによる停電時に電源として使用できる)
そのため、自家消費率が30%以上になるように設備の容量を決めることと、自立運転機能がついたパワーコンディショナーの選定が必要になります。
自家消費型
「自家消費型」とは、太陽光パネルで発電した電気をすべて自社で使用することを目的とした方法です。
自家消費型太陽光発電では売電をしないので、直接収入が増加することはありません。その代わり、電気代削減・節税・脱炭素経営などさまざまなメリットが得られます。
近年は、住宅用太陽光発電・事業用太陽光発電ともに自家消費型が主流になっています。
売電型から自家消費型が主流になっている理由
買い取り価格が低下している
太陽光発電で電気を売るためには、固定価格買取制度(FIT)の認定を受けなければなりません。
固定価格買取制度における売電単価は、認定を受ける年度ごとに設定されています。たとえば、2012年の10kW以上50kW未満の設備の売電単価は40円/kWhでした。
しかし、売電単価は年々低下し、2023年に10kW以上50kW未満で認定を受けた場合の売電単価は10円/kWhまで低下しました。
太陽光発電設備の導入費用も低下しているとはいえ、売電型の太陽光発電にメリットを感じにくい状況になったことは間違いないでしょう。
また、2020年度以降は、先述したように10kW以上50kW未満の全量売電ができなくなったことも、売電型の新規参入が現実的ではなくなった要因です。
将来的に電気を売るより使う方がお得になる
売電型から自家消費型への移行が進む理由のひとつは「売電するより使ったほうがお得になるから」です。
産業用太陽光発電は、固定価格買取制度(FIT)を利用した全量売電型を中心に普及してきました。しかし、先述したように、固定価格買取制度における売電価格は年々低下しています。
2023年度の産業用太陽光発電の売電単価は、低圧(10kW以上50kW未満)の場合「10円+税」です。一方、関西電力の法人向け「従量電灯B」プランの料金単価は「17.91円」です。
つまり「作った電気を10円で売るよりも、17.91円で買うはずだった電気を削減するほうがお得」ということです。
このように、太陽光発電では発電した電気を売るよりも、自社で使用したほうが経済的メリットが出やすい状況に変わったといえます。
非常用電源としてBCP対策になる
自家消費型太陽光発電を導入すれば、自然災害などによる停電時でも、日中は非常用電源として活用でき、BCP対策に役立ちます。
BCP対策とは、企業が自然災害や感染症流行などの非常時に、事業の被害を最小限にとどめ、早期復旧するための方法を取り決めておくことです。
BCP対策のひとつが停電対策であり、自家消費型太陽光発電を導入することで、照明やパソコンなど、最低限の設備を起動させられるため、事業の早期復旧に繋がります。
また、蓄電池を併用すれば、日中だけでなく夜間のや停電時にも一部の電気を使用できます。
余剰売電か自家消費、どちらを選ぶべき?
これに関しては、企業ごとに最適な導入方法は異なります。
余剰売電に向いている企業の特徴
余剰売電に向いている企業は、休日が多かったり、施設自体の電力消費がそこまで多くなかったりなど、太陽光パネルで発電した電力を消費しきれず余りが発生するような企業です。
このような場合、余った電気をただ捨てるよりは売電したほうが、経済的にメリットが出るケースがあります。たとえば以下のような企業が該当します。
- ドラッグストア
- 衣料品店
- 運送業の倉庫
- 小規模のカフェなどの店舗 など
自家消費に向いている企業の特徴
自家消費に向いている企業は、施設の消費電力が多くて屋根が広いなど、太陽光パネルで発電した電力を余すことなく消費できる企業です。たとえば以下のような企業が該当します。
- 年中無休の中規模以上の店舗
- スーパーマーケット
- 冷凍冷蔵倉庫
- 消費電力が大きい機器を使用する工場 など
自家消費・余剰売電の判断には現状の把握が大切
太陽光発電を導入して自家消費・余剰売電のどちらを適用するか判断するためには、導入する目的を明確にし、現状の電力使用状況を把握することが大切です。
- いま、自社でどれだけの電気を使っているのか?
- 最も電気をたくさん使っている時間帯は?
- 電気を使用する施設の稼働状況は?
- 年間を通しての電力使用状況の傾向は?
上記を把握することで、どれくらい電気代削減効果が見込めるのか、どのような設計がもっとも効率的なのかを判断できます。そこから「自家消費と余剰売電のどちらがいいのか?」を検討していきます。
お客さま自身で判断することが難しい場合は、太陽光発電の業者に相談しながら事業計画を進めていくことをおすすめします。
【2024年から】企業の屋根設置型太陽光は通常より高く売電できる見込み
経済産業省は、2024年度のFITにおいて、工場や倉庫など、企業の屋根に設置した太陽光発電システムによる売電価格を通常より高く設定する方針です。
具体的には、10kW以上50kW未満の太陽光発電システムの場合、地上設置の10円/kWhに対し、屋根設置では12円/kWhで設定される見込みです。
太陽光パネルを設置する場所で買取価格に差をつけるのは初の試みです。今回の決定は、工場や倉庫などに設置する場合の、足場などの建設コストが考慮されたとみられます。
企業の屋根面積や電気使用量などの条件によっては、余剰売電の方が相性が良いケースもあるため、上記の決定によって多くの企業が太陽光発電を導入しやすくなることが期待されます。
自家消費型の太陽光発電を導入する際のポイント
企業が自家消費型太陽光発電を導入する際、気をつけておきたいポイントを紹介します。
建物の状況
屋根に太陽光パネルを設置する場合、以下のように、建物の築年数や耐荷重などの条件を確認する必要があります。
- 自社の敷地内に太陽光パネルを設置するスペースが豊富にある
- 建築基準法の「新耐震基準」を満たしている
- 建物が新耐震基準を満たさない場合は耐震補強をしている
電力の使用状況
自家消費型太陽光発電を導入する際は、可能な限り「発電した電力を余すこと無く自社で消費できる」ことが重要です。
太陽光発電の設置を依頼する業者とよく相談し、現在の自社の電力使用状況を把握するところから始めましょう。
補助金の申請
企業の太陽光発電導入に対して、国や自治体からの補助金が設けられています。補助金を利用できれば、投資回収年数を早められます。
補助金申請をするうえで注意したいのが「申請までのスケジュール」です。事業用太陽光発電の補助金の多くは、春ごろに募集を開始します。
しかし、太陽光発電の導入準備は業者選定や現地調査・仕様確認・補助金申請の準備を含めると、4カ月から5カ月かかるケースもあります。
つまり、補助金を導入して事業用太陽光発電を導入したい場合、前年度の秋ごろから業者選定に動き出すことがベターであるということです。余裕を持って事業計画を進めましょう。
当社による太陽光発電導入事例
余剰売電の太陽光発電導入事例

- ブランドイメージの向上と収益性の向上を実現したい
- 自家消費による電気料金削減と余剰電力の売電による新たな収益源の確保
- 販売店でのCO2環境負荷軽減の取り組みによるブランディング効果
「ホンダカーズ石見浜田東店」さまでは、自家消費による電気料金削減と余剰売電による収益源の確保を目的として導入させていただきました。
また、脱炭素と関わりが大きい自動車業界の企業ということも踏まえ、CO2排出削減によるブランディング効果も狙いとしています。
自家消費の太陽光発電導入事例

- 工場のBCP対策や、電気代削減によるランニングコストの削減
- 事業継続力強化計画認定取得(BCP対策)
- 工場での電気使用量を約30%削減
「株式会社瀬戸水産」さまは、自家消費型の太陽光発電を導入することで自社のBCP対策を強化に繋げております。
また、導入のタイミングが良かったため、2022年からの電気代高騰の影響を抑えることができたという感想もいただきました。
まとめ
太陽光発電は大きく、全量売電型・余剰売電型・自家消費型の3つに分けられます。制度の内容変更などにともない、全量売電型が縮小し、自家消費型が主流になっています。
電気代の削減をしながら、脱炭素経営やBCP対策にも繋がる自家消費型太陽光発電は、今後も導入が増加していくでしょう。
企業の太陽光発電導入は当社にお任せください
株式会社ハウスプロデュースでは、企業向けに太陽光発電に関するご相談を承っております。
- 累計6,500件以上の太陽光発電システム施工実績を積むなかで培ったノウハウを活かして最適な設計を行います。
- 屋根修繕事業も行ってきたため、屋根の知識も豊富です。設置可否の判断や屋根へのパネル設置に関しても安心してお任せください。
- 施工力を活かして強度が高い設備を導入するほか、10年間の施工保証を設け、お客様の安心に繋げています。
- 中小企業が利用できる補助金や税制の調査・申請サポートが充実しており、お客さまの手間を最小限に抑えます。
導入を検討されるお客さまには、電気使用量などお伝えいただければ無料で導入効果をシミュレーションいたします。太陽光発電にご興味がある方は、まずはお気軽にお問い合わせください。