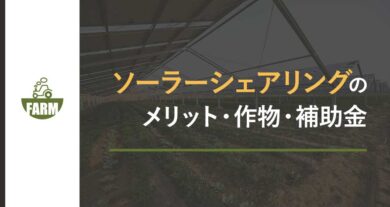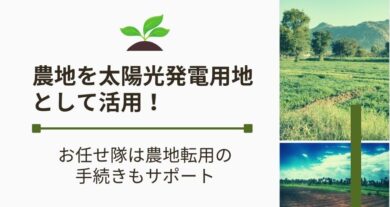ソーラーシェアリングは農地上での太陽光発電と農業の共存を目指す取り組みで、環境保全と経済的利益を両立させる次世代の農業モデルとして注目されています。
しかし、農地にソーラーパネルを設置することによる作物への影響や、手続きの複雑さなどに懸念を抱く方もいます。
そこで今回は、ソーラーシェアリングで失敗しないよう、どのようなポイントに注意しなければならないかを解説しつつ、ソーラーシェアリングの成功事例なども交えながら詳しく紹介します。
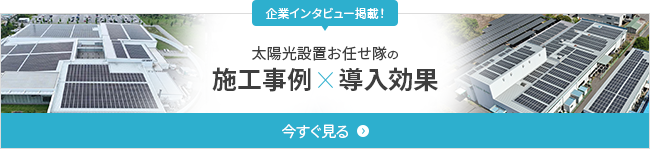
目次
ソーラーシェアリングの基礎知識

はじめに、そもそもソーラーシェアリングとは何なのか、基礎知識として仕組みや制度を利用するうえでの条件などを解説します。
ソーラーシェアリングとは
ソーラーシェアリングは、「営農型太陽光発電」とも呼ばれ、農地上にソーラーパネルを設置して太陽光を農作物の育成と発電に同時に利用する取り組みです。
この方法で農業と発電を両立させるため、「ソーラーシェアリング」と呼ばれます。
また、ソーラーシェアリングによって発電した電力は、「再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT制度)」を利用して、20年間の一定価格で電力会社に 売却することが可能です。
ソーラーシェアリングにより、農業による収入と売電による収入の双方を得ることが可能でき、農地の新たな収益源として導入が増加しています。
ソーラーシェアリングを行える基準
自身が所有する農地に太陽光発電を設置してソーラーシェアリングを行うには、下記の基準を満たす必要があります。
- 農業を行っている(営農している)こと
- 農地法に基づく農地の一時転用許可を受けていること
ソーラーシェアリングを行う上でとくにつまずきやすいのが、農地法に基づく農地の一時転用許可を受けていることです。
農地の一時転用許可における基準
農林水産省では、ソーラーシェアリングを行うための「農地の一時転用の許可」を受けるにあたり、以下の基準が設けられています。
- 営農を適切に継続したうえで、支柱が発電設備を支えるためのものとして利用されること
- 生産された農作物に係る状況を毎年報告すること
- 営農の適切な継続が確保されなくなった場合、または確保されないと見込まれる場合には、適切な日照量の確保などのために必要な改善措置を迅速に講じること
- 発電設備を改築する場合、または廃止する場合には、遅滞なく報告すること
- 営農を行わない場合または発電設備を廃止する場合には、支柱を含む発電設備を速やかに撤去し、農地として利用できる状態に回復すること
【農地の一時転用期間が10年以内となる条件】
農地の一時転用期間は、原則3年間と定められています。転用期間を経過した場合は、更新許可を受ける必要があります。
しかし、下記の条件に該当する場合、転用期間を10年以内まで延長することが可能です。
- 認定農業者などの担い手が引き続き営農を行う場合
- 荒廃農地を活用する場合
- 第2種農地または第3種農地を活用する場合
ソーラーシェアリングの失敗する原因とは
ソーラーシェアリングでもっとも陥りがちな失敗として、下記の2つが挙げられます。
収穫量の低下により事業継続ができなくなる
ソーラーシェアリングでは、営農が主要事業であることが前提です。
ソーラーシェアリングを設置した農地は、その年に収穫した農作物の状況について翌年の2月末までに許可権者(一般的には都道府県知事)に対して報告をする義務が課せられます。
その際、地域の平均単収と比較して収穫量が2割以上減少した場合、ソーラーシェアリングの継続が不可と判断され、設備の撤去を命じられる可能性があります。
思うように作物が育たなかった
ソーラーシェアリングを農地に設置した場合、田んぼや畑の上空にソーラーパネルが配置される構造になります。
そのため、ソーラーパネルによって農地に影が発生して、パネルの下で育てている作物や植物に当たる光量が低下します。その結果、思うように作物が育たず収穫量の条件を満たせず、事業継続が困難となってしまったという失敗例もあります。
なかなか黒字化にならない
ソーラーシェアリングの導入にかかる費用は、発電出力容量50kWに対して1,200万円〜1,700万円が目安です。
ソーラーシェアリングでは、売電収益と営農による収益の2つの収益源が発生するため、細かく収支を計算して綿密な事業計画を立てる必要があります。
一般的には、10年から15年で初期費用を回収して黒字化になるとされています。
しかし、計画に見落としがあれば20年以上経っても黒字化できないという可能性もあります。
ソーラーシェアリングで失敗を避けるためのポイント
ここから、ソーラーシェアリングの失敗を回避するための対策やポイントについて解説します。
営農方法を見直す
もともと日当たりが不十分な農地にソーラーパネルを設置すると、日射量がさらに減少し、作物の収量が下がる可能性があります。
そのため、育成状況を定期的にチェックし、必要に応じて肥料の量や使用回数を調整することが重要です。
さらに、日射量が減少しても影響を受けにくい作物への切り替えも効果的な対策となります。
ソーラーシェアリングと相性が良い作物の一例は下記の通りです。
| 半陰性植物 | ・イチゴ ・ほうれん草 ・小松菜 ・かぶ ・わさび・レタス ・春菊 ・パセリ ・じゃがいも ・さといも・しょうが ・アスパラガス ・長ネギ |
|---|---|
| 陰性植物 | ・みつば ・せり ・クレソン ・しそ・みょうが ・ふき ・にら |
綿密な事業計画を立てる
ソーラーシェアリングの導入に際しては、固定価格買取制度(FIT)の20年という期限を基準に、事業を長期的に継続できるかどうかを考慮することが大切です。
自分の年齢を考慮して、20年後も農業を続けられるか、または家族が農業を引き継ぐかどうかまで事前に計画しておきましょう。
ソーラーシェアリングの成功事例と失敗事例
ソーラーシェアリングを成功させる鍵は、実際にこの取り組みを行っている農家の成功例と失敗例を理解することです。
それぞれの事例から一例を抜粋して紹介します。
成功事例
ソーラーパネル下の適度な日陰は、キクラゲなどのキノコ類の栽培に適しています。
日本では国産キクラゲの流通量が少なく、9割以上を輸入に頼っているため、国産キクラゲの単価は高く安定しています。
このため、広い農地がなくても、限られたスペースで安定した収益を得られるソーラーシェアリングとキクラゲ栽培の組み合わせは成功する可能性が高いといえます。
失敗事例
ソーラーシェアリングには適さない作物として、十分な日射量を必要とする夏野菜が挙げられます。
ナス、トマト、キュウリなどがこの例で、ソーラーパネルの下で栽培すると日射量不足で生育が悪くなるリスクがあります。
これらの野菜を育てている農家では、ソーラーシェアリングによって野菜の成長が遅くなり、収穫量が減ってしまい失敗に陥る可能性が高いといえます。
ソーラーシェアリングに活用できる補助金や支援制度
農林水産省は、「営農型太陽光発電システムフル活用事業」という補助金制度をソーラーシェアリングに取り組む事業者向けに運営しています。
この制度では、ソーラーシェアリングを活用しつつ、電動農業機械や環境制御装置の導入にかかるハードウェアやソフトウェアの経費の一部を補助します。
ただし、太陽光発電設備自体の経費は補助の対象外なので注意が必要です。
また、「民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業」のうち、「新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業」では、ソーラーシェアリングの導入費用の最大2分の1の補助金を受けることができます。
さらに、農業協同組合や一部の金融機関では、ソーラーシェアリングを支援する特別ローンや資金提供も受けられる場合があります。
まとめ
ソーラーシェアリングは農業と発電を両立し、双方で収益を得られる新しいビジネスの仕組みといえます。しかし、あくまでも営農がメインであることに変わりはなく、一定の収量を確保しなければならないという前提があることも覚えておかなければなりません。
ソーラーシェアリングが失敗に終わることのないよう、今回紹介した成功事例やポイントも参考にしながら、導入に向けて検討してみてはいかがでしょうか。