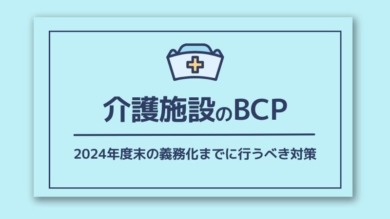近年は自然災害によって長期的な停電が発生するケースが増えており、BCP対策を強化する意味でも、非常用電源の確保を進める法人が増加しています。
とくに自治体・学校・企業・福祉施設・介護施設などの施設は、災害時の事業継続性や避難所としての機能が求められるため、BCP対策の策定・運用が重要です。
この記事では、非常用電源と関わりの深いBCP対策や、企業が発電機・太陽光発電・蓄電池などのシステムを導入するメリットについて解説していきます。
目次
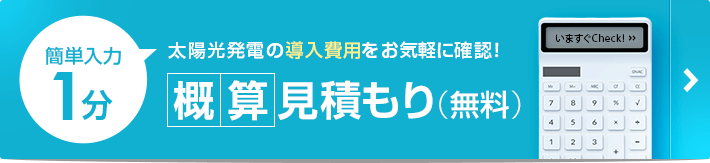
BCP対策とは
BCP(事業継続計画)対策とは、企業が自然災害・感染症・テロ攻撃などの緊急事態において、業務の被害を最小限に食い止め、安全確保や早期復旧のための方法や手段を取り決めておくことです。BCP対策のポイントは以下の5つです。
- 優先して継続・復旧させる中核事業を選定する
- 緊急時の中核事業の目標復旧期間を定める
- 緊急時に提供可能なサービス内容について顧客と事前に協議する
- 事業拠点・生産設備・調達先の代替策を用意する
- 全従業員とBCPについてコミュニケーションを図る
介護事業者は2024年までにBCP対策が義務化される
介護事業者は2024年3月末までにBCP対策を推進することが義務化されています。
2024年3月末までに事業継続計画を作成し、BCP対策の訓練や運用を行う必要があります。また、介護事業におけるBCPはライフラインの確保も必要なので、非常用電源の設置も欠かせません。
そのため、介護事業者は発電機・太陽光発電・蓄電池などの非常用電源の確保が重要な施策となります。
BCP対策で非常用電源確保が重要な理由
停電によって重要な業務が停止するケースが多い
内閣府が、過去の災害で重要な業務が停止したことがある企業に対して調査を行なっています。
そのなかで、災害で重要な業務が停止する要因としてもっとも多いのは「停電(27.8%)」でした。
電気が長時間使用できなくなると、電子機器が十分に使用できなかったり、スマートフォンの充電ができなかったりなどのリスクが発生するため、非常用電源の確保は重要な施策の1つとなっています。
(参照元:令和元年度 企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査(令和2年3月)|内閣府)
大規模な災害では電気復旧までに時間がかかる
BCP対策の重要性が高まっている背景として、地震や台風などの自然災害の被害規模が大きくなっていることがあります。近年に発生した自然災害の停電状況をみていきましょう。
| 名称 | 発生時期 | 停電復旧期間 |
|---|---|---|
| 大阪府北部地震 | 2018年6月 | 約2時間 |
| 西日本豪雨 | 2018年6月末から7月 | 約1週間 |
| 北海道胆振東部地震 | 2018年9月 | 約2日(期間内にブラックアウトが発生) |
| 平成30年 台風21号 | 2018年9月 | 約2週間 |
| 令和元年 台風15号 | 2019年9月 | 約2週間 |
災害の規模や発生地域にもよりますが、ライフラインの中で1番復旧が早い電気でも、完全復旧に1週間以上を要することがあります。
規模の大きい自然災害では、復旧までの時間がかかることを想定して対策を練る必要があります。
停電が企業に与える被害例
2019年9月に発生した台風15号では、千葉県を中心に各地で記録的な暴風となりました。企業の活動にも大きな影響を与え、ソニーの千葉県内工場や日産の神奈川県内工場が一時的に操業停止に追い込まれました。
このように、自然災害による停電は、業種によってさまざまな悪影響と被害をもたらします。また、停電が起きた地域の企業と取引がある場合は、製造業・卸売業を中心に間接的な影響を受ける可能性があります。
通信手段の確保には電源が必要
特に災害の範囲が広域化した場合は、通信手段の確保が重要です。通信手段があれば、情報の保護や回復・従業員の安否確認・取引先との連絡がしやすくなり、指示伝達や次の行動がスムーズに行えます。
実際に、BCP対策を十分に策定していたものの、通信確保ができなかったために事業の回復が遅れたケースも国内外で発生しています。通信手段を確保するための対策は以下2つです。
- 複数の通信手段を併用する(固定電話・携帯電話・衛生電話・メールなど)
- 複数の通信会社やプロバイダと契約する
また、通信手段を確保し、非常時でも利用するためには、発電機・太陽光発電・蓄電池などの非常用電源が必要です。
停電対策に繋がるBCP対策の方法
企業が停電に備えてBCP対策を推進するための方法を解説していきます。複数の受電設備の用意する
災害時に電力が停止する理由の1つに「回線トラブル」があります。回線トラブルを回避するためには、以下2つの方法が考えられます。
-
■予備の回線を用意する本線だけでなく予備の回線を用意することで、片方に障害が出てももう一方の回線に切り替えて電力確保します。■予備の受変電設備を用意する受変電設備とは、高圧の電力を低圧化して建物内の機器で使用できるようにする設備です。これが壊れると電力の供給ができないため、予備の受変電設備を用意して備える方法もあります。
事前に停電時の対応を考えておく
以下の手順で停電時の対応を考えておくことが大切です。
- 各機器の稼働に必要な電力量を調査する
業務に必要な機器の稼働に必要な電力量や、一定期間継続使用するために必要な電力を想定しておくといいでしょう。たとえば停電が3日続くと仮定するなら、3日間で各機器が使用する電力量を考えておきます。 - 停電時に優先的に使いたい機器を選ぶ
次に、停電時でも優先する事業や機器を選びます。たとえば通信手段となる機器や照明設備は、優先度が高いでしょう。 - バックアップ体制を整える
災害・停電の発生時に備えて、ふだんからデータのバックアップを取っておきましょう。作業中のデータだけでなく過去のデータが破損する可能性もあるため、クラウドへの保存や外付けストレージの活用もおすすめです。
発電機を導入する
「ディーゼル発電機」や「ガス発電機」の導入も1つの方法です。
ディーゼル発電機は軽油を使用するため発電効率が良く燃料の単価が安いのが特徴ですが、軽油の保存期間が短いのと排気ガスが出るため環境面では難があります。
ガス発電機の燃料となるLPガスは長期間の保存が可能なため燃料切れのリスクが少ないですが、燃料単価が高いことがデメリットといえます。
太陽光発電・蓄電池
太陽光発電は、火力発電と異なり発電時にCO2を排出せず環境に優しいのが特徴です。また、停電がおきても 太陽さえ出ていれば発電し続けてくれるため、停電対策としても効果的です。
逆にいえば、太陽が出ていなければ電気を供給できないため、停電対策の設備としては不安定な面があります。そのため、BCP対策として導入する場合は後述する蓄電池を併設することでそのデメリットを補う必要があるでしょう。
太陽光発電は、停電対策のほかにも複数のメリットがあります。たとえば自社の電気代削減になるほか、CO2削減による脱炭素経営、税制優遇、屋根の断熱性向上という効果が得られます。
非常用発電機の種類
非常用電源の1つである非常用発電機は、「ディーゼルエンジン」と「ガスタービンエンジン」の2種類があります。それぞれの特徴・メリット・デメリットをみていきましょう。
ディーゼルエンジン
ディーゼルエンジン非常用発電機は、対応できる出力の範囲が広く種類が豊富なため、非常用発電機として使われるのはこちらが多いです。
運転時の注意点として、負荷が低いと煙が出やすいため、出力が大きすぎる種類は選ばないほうが良いでしょう。
| メリット |
|
|---|---|
| デメリット |
|
ガスタービンエンジン
ガスタービンエンジン非常用発電機は、ディーゼルエンジンより小型化が可能で、騒音が少ないタイプです。
本体は小型であるものの、燃料消費が多いため、燃料タンクも含めると設備全体が大型化する可能性があります。また、価格はディーゼル型より高額です。
| メリット |
|
|---|---|
| デメリット |
|
非常用電源としてBCP対策を推進する蓄電池
病院などでは、万が一停電した時の備えとして、一定時間自立して電気を供給できる産業用蓄電池が導入されています。
その他にも、自然災害などにより事業所全体が停電した場合に備えて、サーバーの情報を守ったり、通信手段を確保したりするための非常用電源として産業用蓄電池を導入する企業があります。
また、東日本大震災や近年の災害の状況を踏まえ、非常用電源として家庭用蓄電池を導入する家庭も増加しています。家庭用と産業用の違いは、容量・出力・使用可能な機器・価格などです。
太陽光発電と蓄電池を併用するメリット

停電時に非常用電源として利用できる
太陽光発電と蓄電池を併設するメリットの1つは、BCP対策において重要な「停電時の非常用電源」となることです。蓄電池と併用すれば、さらにこのメリットを活かせます。
太陽光発電設備だけでは、夜間や曇りの日は非常用電源として機能しませんが、蓄電池を併用していれば、発電した電気を貯めておき、夜間や曇りの日に使用できます。
大規模な事業所の場合、全体の電気をまかなうためには産業用蓄電池が必要ですが、高額であるため導入ハードルが高いデメリットがあります。そこで、家庭用蓄電池でオフィスの一部のみ電気をまかなうことを検討するケースもあります。
効率的な電気代削減ができる
太陽光発電や蓄電池をうまく運用すれば、自社で発電した電気を効率良く使用できます。
太陽光発電と蓄電池をうまく活用すれば、日中の電力需要を下げる「ピークカット」や、電力の需要が多い時間に蓄電池に貯めた電気を使用する「ピークシフト」ができ、効率的な電気代削減に繋がります。
燃料が不要
蓄電池は燃料がなくても稼働でき、非常用発電機のような大がかりなメンテナンスはないため、非常用電源よりも導入しやすいといえます。
非常用発電機は種類が豊富で幅広い出力に対応できますが、燃料費が別途かかります。
また、非常用発電機はエンジンを搭載しているため、振動による騒音が大きいことや、定期的なメンテナンスが必要になることがデメリットとして挙げられます。
2024年度は蓄電池の導入が補助金採択のポイントになる
企業・法人が太陽光発電を導入する際、補助金制度を利用できれば投資費用回収期間を大幅に短縮できます。
2023年度から、太陽光発電関連の補助金の一部は、蓄電池を併設して事業に役立てる計画を立てることが、採択のポイントの1つとなっています。
BCP対策を太陽光発電と蓄電池で推進したいと考えている企業の方は、補助金の情報もリサーチしておくことをおすすめします。
まとめ
企業・法人が緊急時の対策をしっかり練っても、非常用電源がなければ思うように実行できない可能性があります。BCP対策にはさまざまなものがありますが、電源の確保はまず検討すべきところでしょう。BCP対策は、非常用電源の確保を含めて構築することをおすすめします。
BCP対策の一環としての太陽光発電や蓄電池の導入はお任せください
株式会社ハウスプロデュースは、非常用電源として活用できる太陽光発電や蓄電池のご提案を行っております。
BCP対策と電気代削減を同時に実現したいというお客さまからも多数のお問い合わせをいただいており、以下の特徴を活かしてご提案いたします。
- 累計6,500件以上の太陽光発電の施工実績を積むなかで培ったノウハウを活かし、発電効率や安全性が高い発電システムを導入します。
- 太陽光発電のみの導入や蓄電池の併設など、お客さまの目的を丁寧にヒアリングし、最適な導入方法を提案します。
- 太陽光発電と蓄電池を導入する際に対象となる補助金の調査・書類作成・申請もサポートいたします。
- 家庭用・産業用問わず多数の蓄電池を取り扱っています。事業所の規模や蓄電池を導入する目的に合わせて製品を選定いたします。
当社にご相談いただければ、無料で導入費用や電気代削減効果などの概算を見積もりいたします。概算見積もりの結果をもとに、導入に関する疑問にお答えいたします。
また、見積もりの結果、設置条件が合わず導入メリットが薄いと判断した場合も率直にお伝えします。無理な営業はいたしませんので、どうぞお気軽にお問い合わせや概算見積もりにてご相談ください。